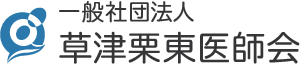2025年05月号 第120話 がん検診してますか
済生会滋賀県病院 消化器内科の保田宏明と申します。2022年10月に着任いたしました。前任地である京都府立医科大学 消化器内科では、主に膵疾患を担当しておりましたので、現在も膵疾患を中心に、幅広い消化器疾患を診療しております。これまでほとんど関わる機会がなかったのですが、当院に赴任してから関わり始めた分野に「がん検診」があります。
ご存じのとおり、わが国の医療水準は先進国の中でもトップレベルにあります。そうであれば、がんの年齢調整死亡率も低水準であることが期待されますが、実際には欧米諸国など他の先進国の方が、日本よりもやや低い傾向にあります。日本は平均寿命が高く、がんは高齢者に多い疾患であることから、「それなら当然では」と思われるかもしれません。しかし、ここで取り上げている「年齢調整死亡率」とは、年齢構成の異なる集団間で公平に比較するために年齢の影響を調整した死亡率であり、高齢化の影響を除外した指標です。日本においても、がんの年齢調整死亡率は1990年代後半をピークに年々減少しているものの、他の先進国ではさらに大きく減少しているというのが現状です。
がんの死亡率を下げるには、「がんにならない」こと、そして「がんを治す」ことの両方が重要です。がんは早期に診断できれば治癒が見込めますが、進行している場合には、最先端の医療をもってしても治癒が困難なことがあります。このことから、医療水準の高さだけでは、がんの死亡率を大きく下げることは難しいということがご理解いただけるかと思います。「がんにならない」ためには、がんの危険因子を取り除くことが求められます。たとえば「禁煙」や「子宮頸がんワクチンの接種」などは広く知られており、今後さらに普及させる必要があります。また「がんを治す」ためには、早期発見が不可欠であり、そのために重要なのが「がん検診」です。国が推奨するがん検診は、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんの5つです。なかでも大腸がんの年齢調整死亡率が他の先進国に比べて高い理由の一つに、日本の大腸がん検診の受診率の低さが指摘されています。わが国のがん検診は、市町村が実施する住民検診(対策型検診)、企業や保険者が実施する職域検診、そして個人が任意で受ける人間ドックなどの検診で構成されています。そのため正確な大腸がん検診の受診率を把握するのは難しいのですが、概ね40%強と見積もられています。一方、英国や米国では50〜60%と、10ポイント以上高い水準にあります。さらに検診の手法についても、わが国では便潜血検査が主流である一方、米国では大腸内視鏡検査も積極的に取り入れられており、これが死亡率の低下に寄与している可能性があります。
私は消化器内科医として、大腸がん検診、胃がん検診、さらには膵がん検診にも携わり、がん検診の普及と受診率向上に努め、草津・栗東地域におけるがん死亡率の低下に貢献できればと考えております。なお私事ではございますが、本年8月に開催される「第54回日本消化器がん検診学会 近畿地方会」の会長を拝命し、「消化器がん検診の現状と課題」をテーマに現在準備を進めております。ご興味のある医療関係者の方々は、ぜひご参加いただければ幸いです。また一般市民の皆様には、当院主催の市民公開講座などを通じて、がん検診の大切さをお伝えしてまいります。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
保田 宏明(済生会滋賀県病院 消化器内科)