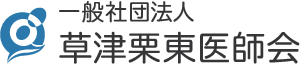2025年03月号 第118話 「当たり前」を学校で教える意味
当クリニックは、地域における訪問診療などを通して、自宅や施設におられる方々の支援をさせて頂いております。私は整形外科専門医ですが、内科、総合診療科、救急集中治療科の医師などが患者様の診察を担当しております。高齢化が進むなか、老衰の死亡率が悪性新生物、心疾患に次いで3位となりました。多くの方が安らかに天寿を全うできるよう、地域医療に貢献して参ります。今後とも忌憚のないご指導、ご鞭撻をお願い申し上げます。
さて、私には大学生になる娘がいますがその子育てを通して感じた事のうちの一つについて感じたことを少々書かせて頂きたいと思います。私は幼い頃から手芸や工作、裁縫が好きで得意でした。幼稚園や小学校で使う手提げ袋や雑巾、時に服を縫ってくれた母や、日曜大工が趣味の父の影響だと思います。それ以外にも調理や掃除、栽培、子育てや家計など生活に密着した知識や経験は両親や祖父母をはじめ周囲の大人から自然と学んだことが多いと思います。そして小学五年生から学校の授業の技術家庭科でもそれらを学ぶことができました。私は実習もあるこの授業が大好きで楽しみながら受けた記憶と、グループで作業する事の難しさを実感した記憶が残っています。
しかし家庭で身につけられるいわば当たり前のことをなぜわざわざ学校でも時間を割いて教えるのかと疑問思った記憶もあります。おそらく高校生の頃だったと思います。当時の私は楽しかったこともありおそらくあまり深くは考えておらず「何気なく伝承されている技術・知識の科学的な裏打ちや深掘りをしたり、実習はグループ作業の練習にもなっているのかも」などと考えていました。友人の中には定期テストに組込まれていることに疑問を訴える人もいました・・・受験に必要ないのに、と。我が娘もそうでした。娘にとって家庭科はどちらかというとつまらない科目でありなぜテストがあるのだろうと。娘とそんな話をしたことをきっかけに調べてみると、技術家庭科の授業時間が自分の学んだ頃と比べ想像以上に少なくなっていることに驚きました。これでは確かに実習で浴衣などを縫い上げることはできません。そして同時にこの分野の知識や技術は自分が習った頃より家庭環境に大きくゆだねられてしまっているのではないかということにも気づきました。私ができないことは娘もできるようにならないかもしれない、つまり「親が知らないと子供も知らない」という連鎖が生まれてしまうのです。
そこで改めて「家庭で当たり前のこととして身につけられることをなぜわざわざ学校でも時間を割いて教えるのかという疑問」に立ち返ってみると、周囲に家事などの知識や経験を豊富に持つ親などが周囲にいる環境は実は当たり前ではないことに改めて気づかされました。そしてもし親が知らないという理由で「当たり前といわれること」が家庭では身に着けられなかったとしても、学校で学び経験することができれば「親が知らないと子どもも知らない」という連鎖を断ち切れる、そういった役割も技術家庭科にはあるのではないでしょうか。衣服はもちろん今は「手作り風」手提げ袋などは店舗やネットでも購入できるし雑巾などは身近なホームセンターやスーパー、100円ショップなどで簡単に手に入れることができます。そう考えると裁縫は、現代においては必ずしも必要な技術ではないのかもしれません。それより近年目まぐるしく変化している情報化社会に対応した分野の教育にもっと力を入れる必要があるのかもしれません。学習指導要領の項目を見るとこういった時代の変化に合わせて対応していることもわかりました。
「当たり前」なことは学校で時間を割いて教えなくてもいいのではないかという考えもあるかと思います。しかしそのような「当たり前」の事の方が実は格差が生まれやすく、もしかするとその格差は気づかれにくいかもしれません。だからこそ私は技術家庭科の授業をはじめ生活に密着した経験や知識・技術を教える課程は、時代の変化による見直しを続けながら今後も存続してほしいと思っています。そしてこの知識や技術を必要としている子供たちに届くことを願っています。
一杉尚子(湖南サポートクリニック)