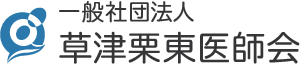2025年10月号 第123話 新たな地域医療構想のあれこれ
地域医療構想って何だっけ
淡海ふれあい病院の院長の平野です。2004年に滋賀医科大学から旧草津総合病院に赴任し、外科医として地域の第一線で活動してきました。草津栗東医師会には20年以上にわたり所属し、現在もお世話になっています。医師会の先生方との繋がりや交流は私にとって貴重な財産であり、現在病院の要職で仕事できているのもご指導ご支援の賜物と厚く感謝申し上げます。私が2014年に旧草津総合病院の院長になって以来、地域医療構想への取り組みは頭の痛い難しい課題でした。地域医療構想は2016年に厚生労働省が発出し、2025年に向けて病院ごとに病床数を調整することを目的としていました。2次医療圏ごとに病院間で相談し、推定されている医療需要にあった必要病床数に変更することを求めてきたのです。地域や病院によっては病床数の削減や病院の統廃合が必要となり、地域医療の衰退、崩壊に繋がるとして社会問題となったのは記憶に残る所です。一方、病院には一層の機能分化・連携も求められました。
かつての旧草津総合病院は比較的短期間に急成長した病院であり、上意下達の縦割りの組織であるが故、改革には疎い巨大なケアミックス病院でありました。しかし、地域医療構想の登場により、病院改革が一挙に進むことになります。構想では病院単位で機能分化や病棟再編が条件となっていました。719床の旧草津総合病院は直ちに病院の分離・分割に着手したのです。2015年に100床の介護療養病棟を草津介護医療院に、2020年に草津総合病院を199床の淡海ふれあい病院と420床の本院に、やがて本院は淡海医療センターとなりましたが、1施設と2病院に分離したのです。その結果、急性期医療、慢性期医療、介護医療にそれぞれ特化した現行の病院が誕生しました。現在の医療は情報伝達や医療機関連携が進んでおり、かつて推奨された病院完結型医療は過去のものになっています。むしろ、社会医療法人誠光会が中心となった地域完結型医療の推進や介護施設を巻き込む医療介護連携の強化を目指し、地域密着型の医療を展開しているのです。
コロナ過で地域医療構想も吹き飛んだ
2020年から始まった新型コロナ感染症は地域医療構想の不備と地域医療の提供体制の弱点を直撃することになりました。地域医療構想は平時の医療需要に対応した医療資源の適正配置を前提にしており、そもそも感染症の蔓延などは想定もしていません。病院においても新型コロナ感染症における外来、検査、入院の対応は未知の領域であり、国や自治体からの指示、指導がないと簡単には動くことはできなかったのです。地域医療構想は医療の効率性や持続可能性を追求していますので、迅速な対策や特殊な領域の治療が必要となる新型感染症には無力だったのです。国をあげた新型コロナ感染症対策は5類に移行する2023年までは続きましたが、あれほど議論されていた病院の統廃合や病床の削減の話しは鳴りを潜めていたように思います。その後、国は第8次医療計画では5疾病5事業に新興感染症対策を1事業として追加し、6事業としました。果たして100年に一度といわれた新興感染症の出現と世界的大流行の経験は、これからの次世代の感染症対策にどのように生かされていくのでしょうか。一方、医療機関に支給されたコロナ補助金は巨額であり、病院経営の追い風となりました。改めて命を守る医療にはお金がかかることが実証されたと思います。
地域医療構想の最終年度は大変な年!
2025年は地域医療構想の最終年度に当たります。ところが、今の病院経営はどうなっているでしょうか。大変なことが起きています。病院の閉鎖あるいは倒産、地域医療の危機が目の前に迫っています。病床の調整や変換、病院間での協力などは絵に描いた餅、病院経営は深刻な状況に陥っているのです。公的病院の8割以上が赤字、私の病院も利益率で昨年に比し3~5%の減益となっています。患者は増え、仕事量や範囲も拡大する中で、頑張るほど利益が減っていく、この状況は看過できないと思います。最近の日本医師会の報告では診療所の経営も大層厳しいと報道されています。私たちの収入の源である診療報酬のあり方に根本的な問題があるのです。社会は物価や需要に呼応して価格が決まり収入が維持されています。私たちも経営者であり家族や職員の生活を維持するとともに、医者としての使命、役割を果たし、地域医療を守り社会貢献を続けることが求められています。医師会の皆さんには病院とともに、適正で、あるべき体系の診療報酬が構築されるよう主張し、行動していただきたいと思います。
新たな地域医療構想は開業医の先生方も主役!
2026年度から新たな地域医療構想がスタートします。新構想の大きなテーマは85歳以上の人口増加です。コンセプトは85歳以上の増加や人口減少が進む2040年とその先を見据え、すべての地域・世代の患者が適切に医療介護を受けながら生活し、必要に応じて入院
となっています。2040年はこれから15年先のことかと思われますが、現実はそう甘い話ではありません。淡海医療センターの救急外来を受診された2024年1年間の約4000名の患者と2025年1月から6月までの65歳以上の入院患者、1145名について検討しました。
10歳ごとの年齢層で受診患者数を見ますと、80歳代が最も多く、次いで90歳代でした。入院患者数も同様の傾向であり、これらの年齢では重症・重篤患者割合が80%を越えていました。入院に至った高齢者を5歳ごとの年代で分類すると85~89歳が最も多く、続いて90~94歳となり、75歳以上の後期高齢者が大半となっていました。緊急で受診する患者とその後入院に至る患者の多くは85歳を超える高齢者なのです。さらに、当然ではありますが、より重症化した高齢者が増加しているのです。最近、救急搬送患者が増え救急の在り方、特に高齢者救急が問題となっています。高齢化率が22%と若い世代の多い草津市でも85歳問題と高齢者医療は重要な課題であり、早急な対策を講じる必要があります。
新構想では従来の「入院医療」に加え「外来医療・在宅医療」、「介護との連携」などが加わりました。やっと地域全体の医療提供体制を議論し提供できる環境が整ったと感じています。多くの患者は地域の開業医の先生方にお世話になっています。先生方は患者さんにとって身近な存在であり、治療や健康管理だけでなく福祉や生活支援なども担当されています。病院は入院医療が主ですが、その他の領域の医療は住民とつながり、地域を知る開業医の先生方の得意分野でもあります。高齢者医療では「治し支えること」が目標となり、病気を治すことも大切ですが、今の患者の生活を維持し個々の人生を支えることがより重要となっています。「時々入院、ほぼ在宅」と言われるように、自宅で過ごす高齢者が増え、過度に病院に依存することのない地域包括ケアシステムが構築されることが望まれます。多死社会の中では、ACPの普及・浸透とともに在宅・施設看取りの拡充が必須です。このように、開業医の先生方の役割が一層重要になるとともに、新たな地域医療構想では開業医の先生方も主役の一人として活躍していただきたいのです。
2040年のあるべき未来予想図
これからの日本は大きな人口動態の変動により医療の需要と供給に大きなギャップが生じ、安定的・持続的な医療機関の運営が困難となります。今こそ利害関係を乗り越え高所大所から予測データに基づき客観的判断で行動すべきでしょう。人口減少地域では行政が強制力を持ち病院の統廃合と連携推進法人による効率的運用が望まれます。比較的人口が維持される地域では積極的に民間資本を導入し病院間のホールディングカンパニー化と最適な医療体制の構築が必要です。いつまでも公的資金の注入を続けることはやめるべきです。地域医師会は大学や病院とともに地域の医師および診療科偏在に取り組むべきでしょう。自由な開業もいいですが、将来的な医療提供のバランスや医療機関との連携には十分に配慮すべきです。医師会に加入することを必須とし、活力ある強靭な医師会を目指していただきたいと期待します。病院やクリニックは公共財であり、医療者はエッセンシャルワーカーです。国民の皆様には医療はお金のかかるものと再認識していただき、2040年に向って持続可能な医療提供を構築できるよう広く理解と支援をお願いしたいと思います。
平野正満(社会医療法人誠光会淡海ふれあい病院 院長)